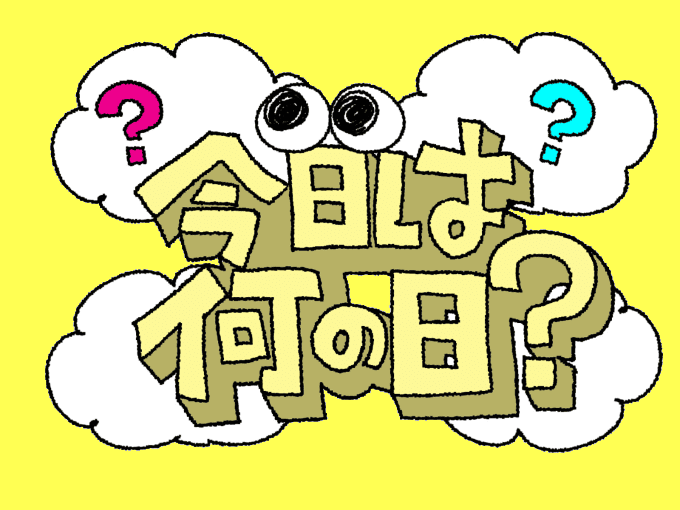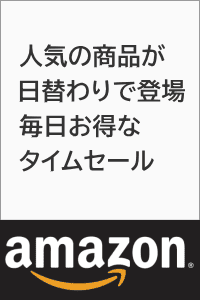令和7年1月~6月の
イベント・記念日等
2025年1月~6月の記念日・イベント、おもな二十四節気の月日を掲載しています。
※4月16日現在、目次の機能が正常に動作しないようです。お手数ですがスクロールで各項目までの移動をお願いいたします。
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 4月 | 5月 | 6月 |
2025年はどんな年?
2025年(令和7年)は昭和が始まった1926年(昭和元年)12月25日から、100年目になり大きな節目になります。政府は「昭和100年政策推進室」を設置しており、記念事業などは2026年(令和8年)に行われるようです。また太平洋戦争が終結した1945年(昭和20年)8月15日から80年です。
- 1月にJR東海の新幹線点検車両「ドクターイエロー」が引退。西日本は2027年の予定。
- 今年の「節分」は2月2日(日)、「立春」は3日(月)です。
- 3月22日にNHKラジオの放送が始まって100年。
- 4月13日から「日本国際博覧会」が大阪府で開催されます(10月13日まで)標語は「いのち輝く未来社会のデザイン」
- 9月13日から「第20回世界陸上(国立競技場)」が開催。
巳年の著名人
その他
- 「2025年問題」コンピューターで昭和100年を昭和0年と誤って認識することによる問題。また 団塊の世代が後期高齢者(75歳以上)になる。
- 太陽が太陽極大期になり、大きな太陽フレアが発生し地球に直撃した場合、無線通信や電力網などが影響を受ける可能性あるということです。

1月5日(日)は「小寒」
今日から寒の入り。寒さが厳しくなる頃です。2月3日(月)の「立春」まで寒の期間です。
1月7日(火)は「七草」
「セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ」です。
 |
 |
▲画像は拡大表示します。
1月12日(日)は「初巳」
今年初めての「巳=へび」の日。今年は「巳年」ですね。
1月13日(月)は「成人の日」
「成人の日」を迎えられる方、おめでとうございます。
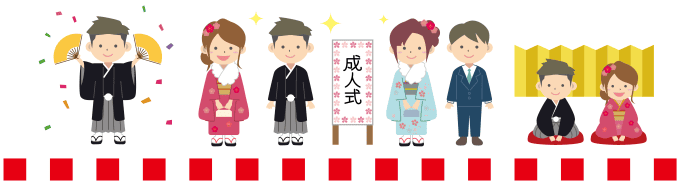
1月17日(金)は「阪神・淡路大震災の日」
甚大な被害が発生した地震から30年になります。
 |
 |
▲画像は拡大表示します。
発生時刻は午前5時46分です。この地震による被災地域の死者は6,434人、行方不明は3人、負傷者は4万3792人、建物の前回は10万4906棟とされており、甚大な被害でした。
この年は3月にオウム真理教による「地下鉄サリン事件」も発生しており、社会不安が多かった年です。11月に日本でWindows95が発売されインターネットへの接続も容易になりました。(民間にインターネットが解放されたのは少し前ですが、95年は実質的な普及が始まった年です)
1月18日(土)は「都バスの日」
1924年1月18日に東京市営乗合バスが営業を開始した日
また今から56年前の1969年1月18日に全学共闘会議(全共闘)および新左翼の学生が東京大学の「安田講堂を占拠した事件が発生し、翌19日に警視庁が機動隊を突入させ封鎖解除。
1月20日(月)は「大寒」
この日から1年でもっとも寒い期間と言われます。実際に多くの地域で最低気温がもっとも低くなるのは1月下旬です。
いつまで寒いの?(全国おもな都市の最低気温が初めて10℃を超える平年日)>>
またアメリカ合衆国大統領就任式が行われ、トランプ大統領が就任。
1月22日(水)は「カレーの日」
全日本カレー工業協同組合が2016年に制定。写真は懐かしい元祖ボンカレー。
1月26日(日)は「文化財防火デー」
1949年1月26日に法隆寺金堂壁画(奈良・法隆寺金堂の壁面に描かれていた仏教壁画で、不審火により大半が焼失)が焼損したことをきっかけに、文化財保護を警察するために文化庁と消防庁が制定。

2月2日(日)は「節分」
今年は「立春」が2月3日(月)のため、節分は3日です。豆まきして夜に、その年の恵方に向かって無言で願い事を思い浮かべて、丸かじりすると願いが叶うとされています。

2月3日(月)は「立春」
少しづつ気温が上がり始めます。しかし3月までは寒暖差が大きい日が続きます。
2月7日(金)は「北方領土の日」
1980年(昭和55年)に制定され45年です。
2月11日(火)は「建国記念の日」
建国は紀元前660年2月11日とされているため2685年になります。
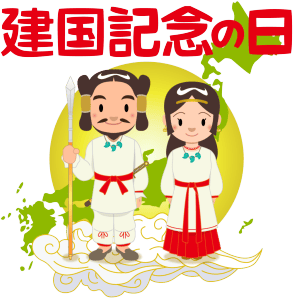
2月14日(金)は「バレンタインデー」
チョコもらえるといいね。
2月22日(土)は「猫の日」
猫の日実行委員会が1987年に制定したということです。

2月23日(日)は天皇誕生日
第126代天皇 徳仁様のお誕生日です。1960年〈昭和35年〉2月23日のご誕生で65歳をお迎えになられます。

3月1日(土)から「春の全国火災予防運動」
3月1日(土)~7日(金)まで実施されます。この時期は空気が乾燥し風の強い日も多くなります。建物火災、林野火災などすべての出火件数では3月がもっとも多くなります。火災の怖さは延焼による近隣への被害拡大、1度に複数の死傷者が発生するケースも少なくないことです
3月3日(月)は「ひな祭り」
「耳の日」でもあります。
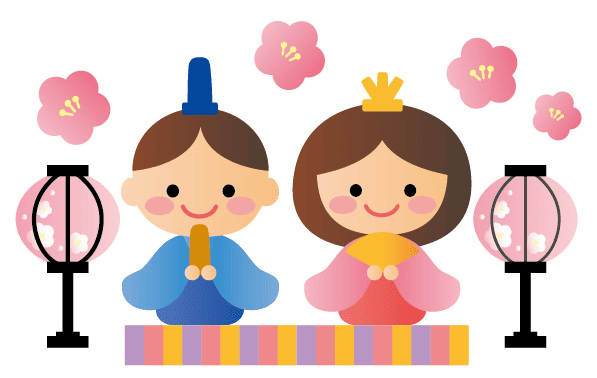
3月5日は「啓蟄=けいちつ」
日中の気温も上がり土の中の虫も出てくる頃です。
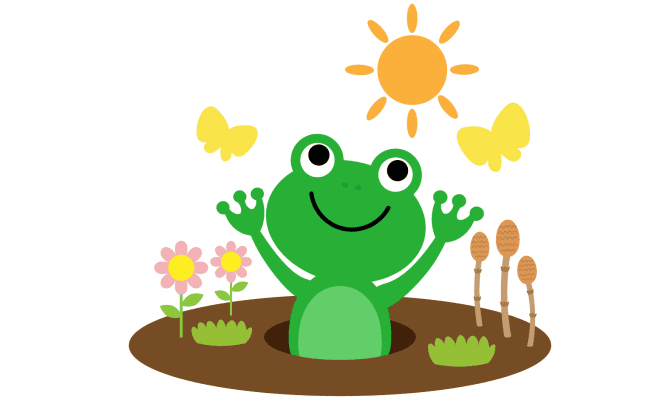
3月10日(月)は「天赦日」
今年最初の「天赦日」です。また「一粒万倍日」「寅の日」とも重なります。なにか良いことがあるといいですね!

3月11日(火)は「東日本大震災の日」
未曽有の地震災害から14年です。

3月20日(木)は「春分の日~春の彼岸」
彼岸入りは17日(月)彼岸明けは23日(日)です。

3月22日(土)は「放送記念日=ラジオ放送100年」
今年は日本で初めてNHKラジオ放送が始まって100年です。

4月8日(火)は「花まつり」
灌仏会(かんぶつえ)ともいわれ、お釈迦様のお誕生日です。
4月13日(日)から「日本国際博覧会」
本日より大阪府(夢洲=ゆめしま)で「日本国際博覧会」が開催されます。期間は4月13日-10月13日の184日間です。

▲会場となる「夢洲=大阪市此花区。現在は建設中です。
4月29日(火)は「昭和の日」
昭和天皇のお誕生日でした。今年は昭和換算で100年目の年ですね。
GWの始まりでもあります。2025年GWのカレンダーの並びです。
| 4月29日(火) | 4月30日(水) | 5月1日(木) | 5月2日(金) |
| 昭和の日 | |||
| 5月3日(土) | 5月4日(日) | 5月5日(月) | 5月6日(火) |
| 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 | 振替休日 |


5月1日(木)は「八十八夜」
「立春」から88日目の日です。

5月3日(土)は「憲法記念日」
1947年(昭和22年)に日本国憲法が施行されたことを記念する日です。
5月4日(日)は「みどりの日」
昭和天皇が植物に造詣が深く、自然愛されたことから「緑」とされたということです。
5月5日(月)は「子どもの日」
端午の節句ですね
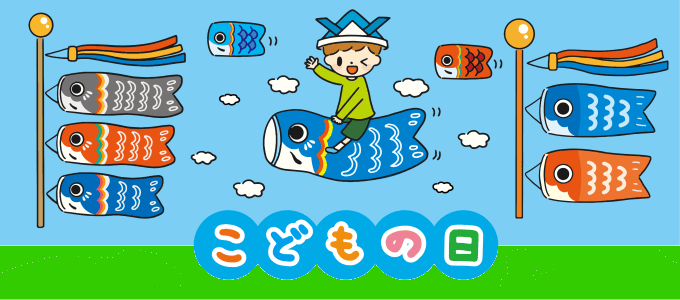
5月10日(土)から「愛鳥週間」
期間は5月10日(土)~5月16日(金)です。

5月11日(日)は「母の日」
日頃の母の苦労をねぎらい、母への感謝を表す日です。
5月25日(日)は「天赦日」
今年2回目の「天赦日」です。なにか良いことがあるといいですね。


6月1日(日)は「気象記念日」
この日は「電波の日」「写真の日」「人権擁護委員会の日」「鮎(あゆ)の日」でもあります」
6月10日(火)は「時の記念日」
日本で初めて時計(水時計)による時の知らせが行われたことを記念した日です。

6月15日(日)は「父の日」
アメリカで「母の日」にならって、父親に感謝するために白いバラを贈ったのが始まりとされています。
6月21日(土)は「夏至」
日の出から日没までの時間が長くなります。
2025年の「二十四節季」早見表
立春から大暑まで
| 2月~4月 | 5月~7月 | ||
| 立春 (りっしゅん) | 2月3日 | 立夏 (りっか) | 5月5日 |
| 雨水 (うすい) | 2月19日 | 小満 (しょうまん) | 5月21日 |
| 啓蟄 (けいちつ) | 3月5日 | 芒種 (ぼうしゅ) | 6月5日 |
| 春分 (しゅんぶん) | 3月20日 | 夏至 (げし) | 6月21日 |
| 清明 (せいめい) | 4月4日 | 小暑 (しょうしょ) | 7月7日 |
| 穀雨 (こくう) | 4月20日 | 大暑 (たいしょ) | 7月23日 |
- 立春:太陽黄経が315°になる日。暦の上では春の始まりですが、まだまだ寒いですね。
- 雨水:雨水がぬるみ草木が芽生えるころ。
- 啓蟄:冬眠していた虫がはい出す頃。
- 春分:この日から昼の長さが長くなり始めます。
- 清明:花もたくさん咲き始めるころ。
- 穀雨:春の雨が田畑をうるおす頃。
- 立夏:子どもの日のころ。夏の気配を感じ始めるころですね。
- 小満:陽光あたたかく、万物が満足する頃といわれています。
- 芒種:穀物を植える時期とされています。梅雨入りも多くなる時期ですね。
- 夏至:昼と夜の長さがほぼ同じになる日。
- 小暑:日射しが徐々に強くなる頃。
- 大暑:厳しい暑さが始まる頃。多くの地域で最高気温がもっとも高いのは、8月3日~10日頃です。
立秋から大寒まで
| 8月~10月 | 11月~1月 | ||
| 立秋 (りっしゅう) | 8月7日 | 立冬 (りっとう) | 11月7日 |
| 処暑 (しょしょ) | 8月23日 | 小雪 (しょうせつ) | 11月22日 |
| 白露 (はくろ) | 9月7日 | 大雪 (たいせつ) | 12月7日 |
| 秋分 (しゅうぶん) | 9月23日 | 冬至 (とうじ) | 12月22日 |
| 寒露 (かんろ) | 10月8日 | 小寒 (しょうかん) | 1月5日 |
| 霜降 (そうこう) | 10月23日 | 大寒 (だいかん) | 1月20日 |
- 立秋:暦の上では秋の始まり。しかし近年の夏はもっとも暑い時期ですね。多くの地域では8月10日前後から、平年値では気温が下がり始めます。この日以降の暑さは残暑となります。
- 処暑:朝夕は初秋の気配を感じ始めるころ。しかし近年はまだまだ厳しい残暑が続いてますね。
- 白露:草木が朝露に濡れるころ。近年は9月も夏の気温が続いていますが、厳し残暑は和らぎ始めますね。
- 秋分:昼と夜の長さがほぼ同じになる日。お彼岸の中日でもあります。秋の気配も感じるころで、だいぶ過ごしやすくなります。ちなみに9月は多くの地域で、月初と月末で日没時間の差が大きい月です。
- 寒露:秋も深まりはじめ、朝晩は肌寒さを感じはじめます。
- 霜降:各地で朝露が見え始めるころ。多くの地域で平地の木々の葉が赤黄色に染まり始めるころです。
- 立冬:朝夕は肌寒さを感じ、平地でも紅葉の鮮やかさが増すころです。
- 小雪:晩秋のころで日中の気温もだいぶ下がり、東・西日本でもコートが必要になる頃です。
- 大雪:日中の最高気温が10℃を下回る地域も目立ち、寒さが厳しくなります。
- 冬至:昼の時間がもっとも短く、日没がもっとも早い日です。かぼちゃを食べてゆず湯につかる日ですね。
- 小寒:寒さの厳しい時期にはいります。立春の前日(節分)までが寒の入り(期間)になります。
- 大寒:1年でもっとも寒い時期ですね。