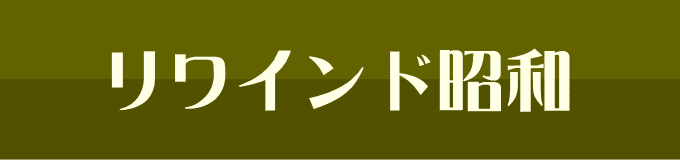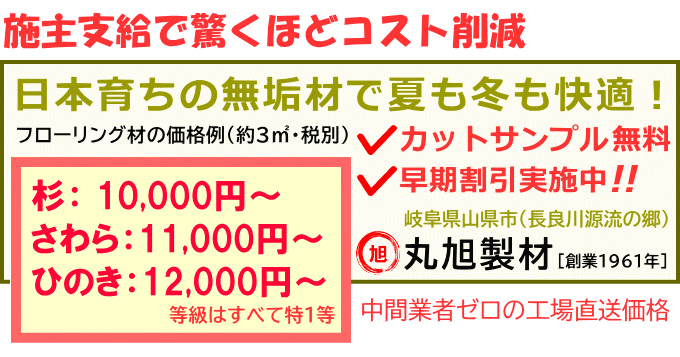9月6日はカラスの日

9月6日は「カラス日=2016年1月5日に日本記念日協会により認定・登録」ということです。由来は英語のCROW=クローと色が黒いからの語呂合わせということです。NHK-FMラジオで東京大学の特任准教授である松原始氏がカラスに関する話をされていました。たいへん興味深い内容だったので掲載しています。すべて同氏が話された内容ではありません。
目次
※一部内容はwikipediaやAI要約を掲載しています。画像はNHK放送とは関係ありません。
日本のカラスについて
国内に定住するカラスは5種類ということです。代表的なカラスは「ハシブトガラス」と「ハシボソガラス」の2種です。
飼育下での寿命は最長で40年でということです。野生で確認されたのは19年だそうです。意外に長生きする鳥ですね。
カラスの名前の由来はカラカラ鳴く、巣をスとしたことが語源のようです。
(1)ハシブトガラス
市街地でもっとも多く見る肉食系カラスです。

くちばしが太いのが特徴で鳴き声は「カァー、カァー」です。市街地から農村まで広く生息し、人間の居住地域でよく見かけるカラスです。夜明け1時間ほど前から活動しはじめるそうです。繁殖期は4月ごろでヒナは2か月ほどで巣離れしますが、しばらくは親鳥と一緒にいるそうです。
雑食性で昆虫や動物の死骸、カエルや魚も食べるそうです。松原氏によるとアリの行列をついばむこともあるそうです。巣をつくる材料は木の枝などが多いですが、ベランダからハンガーを持ち去ることもあるそうです。
(2)ハシボソガラス
市街地にも生息しますが郊外で見かけることが多いカラスです。「ハシブトカラス」に比べると直物系を好むようです。

くちばしは「ハシブトカラス」より細いのが特徴で、大きさもやや小さく郊外の河川や森林を好むそうです。鳴き声は「ガァー、ガァー、あーあー」と濁りのある鳴き声です。繁殖期は3月ごろです。
(3)飼育は可能?
カラスに限らず野鳥の多くは捕獲して飼育は禁止されているようです。ケガなどで保護する範囲では大丈夫のようです。しかしカラスの室内飼育は難しく、部屋にあるものを次々壊してしまうそうです。
(4)頭は良いけどドジな面も併せ持つ
学習能力や記憶力は優れ人の顔を覚え関連性も認識できるそうです。また顔だけでなく服装も覚えることができ、中には1年ほど記憶した例があるということです。また「ハシブト」はモノマネが出来るそうで、人間の言葉を覚えることも出来るそうです。
「ハシホソカラス」はクルミなどを車にひかせ、実を食べる行動も観察されています。また遊びが好きで電線につかまりくるりと回転(大車輪?)したり、斜面を滑る行動も見られます。
頭がいい反面ドジなところもあるようで、エサを咥えて飛んでるとき他のカラスの鳴き声に反応し口を開けたときにエサを落としたり、人間に観察されてることに気づくと、顔だけ隠してしまうなど、お茶目なところもあるみたい。エサと間違え石鹸、ロウソク、ゴルフボール(卵と間違える)を持って行くこともあるようです。
(5)線路への置石は?
松原氏によると線路の下にエサを隠すときに石をどかし、戻すのを忘れた場合があるようです。遊びや電車の走行を妨害する目的ではないようです。
またゴミを荒らすことで嫌がられますね。赤、オレンジ色が狙われやすく、黄色は認識できずゴミネットなどで使われています。
(6)カラスの攻撃
繁殖期の3月~4月は巣に近づく人間を威嚇する行動が見られます。ヒナを守るためですが、最初は鳴き声で威嚇し、次に人間の背後から頭を狙い足で攻撃します。(くちばしをぶつけるとカラスがケガするため使わない)この攻撃自体で人が負傷することはほとんどないですが、驚いて転倒したり階段から落ちるなどの二次被害に気をつける必要があります。

鏡に映る姿を「自分自身」だと認識できないようで、鏡や金属表面(太陽光発電パネルなどもあります)などに映った自分をライバルと間違え喧嘩する様子がみられます。ちなみに「鏡像自己認識」ができる鳥はカワサギで確認されており、ハトも訓練次第では可能なようです。
(7)カラスは食用になるの?
松原氏によると食べられないことはないものの、まずいそうです。日本ではシビエのひとつとして食材の歴史もあるようですが、広く普及しないところからも積極的に食べる鳥ではなさそうですね。また加熱調理しないと寄生虫などのリスクも大きいようです。
カラスの死骸は見つからない?
矢追純一氏(1935年7月17日-)の書籍で「カラスの死骸はなぜ見あたらないのか=初版1993年」がありましたね。「カラスの死骸」という身近で不思議な現象を例に挙げ、科学やメディアが伝える「常識」を鵜呑みにせず、自分の目で見て、感じて、考えることの重要性を説いた内容です。
死骸そのものを見かけることが少ないのは、カラスは体が弱ったり病気になったりすると、外敵から身を守るために人目につかない森や林の中、自分の巣などでひっそりと死を迎えることが多い、街中では自治体による処理が多いためということです。
カラスは神聖な鳥
身近な野鳥であるものの、カラスが大好きという人は多くないかも?しかし日本史の中では”神聖な鳥”として信仰される歴史もあります。
神話に登場する八咫烏
「古事記」や「日本書紀」には、「八咫烏=やたがらす、やたのからす」と呼ばれるカラスが登場します。

神武天皇(初代天皇=紀元前660年|2685年前)が道に迷ったとき、天照(アマテラス)大神の使いとして現れ、道案内をしたという伝承があります。このことから、八咫烏は「導きの神」「勝利を導く神の使い」として信仰されてきた歴史があります。また「熊野信仰」ではシンボルのひとつになっています。
(1)スポーツのシンボル
「導き」や「勝利」の象徴性から、サッカー日本代表チーム(JFA)のエンブレムにも採用されています。ボールをゴールに導くという願いが込められているとされています。
(2)音楽作品では
童謡では野口雨情が作詞した「七つの子」が有名ですね。歌詞を掲載しています(著作権は1995年に消滅)

七つの子の詩[表示する」
- 烏 なぜ啼くの
- 烏は山に
- 可愛七つの
- 子があるからよ
- 可愛 可愛と
- 烏は啼くの
- 可愛 可愛と
- 啼くんだよ
- 山の古巣へ
- 行って見て御覧
- 丸い眼をした
- いい子だよ
その他の楽曲としては同様の「からすの赤ちゃん」、演歌歌手の中澤裕子さんデビューシングルで「カラスの女房=1998年」などがあります。
(3)絵画作品
日本画家の作品では伊藤若冲「烏鷺図屏風」でカラスが描かれています
洋画ではフィンセント・ファン・ゴッホの「カラスのいる麦畑=1890年作」が有名ですね。(作品画像はパブリックドメイン)