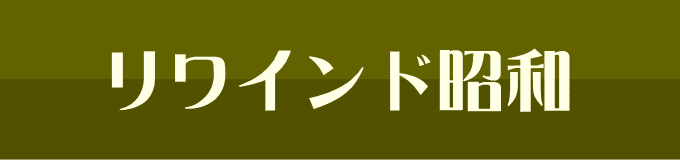美しく咲き天界と地上を
つなぐ赤い花の話

秋の彼岸頃に美しい花を咲かせる「彼岸花」。誰もが知る秋を代表する花のひとつです。
鮮やかな赤に秘められた想い
シダなどの草木の中から一輪だけ咲いたり、他の草花が繁る中に、いつのまにか小さな群れが現れたり‥。河原や土手では大きな群れで咲き誇る美しい姿もみられます。(写真は拡大表示)
 |
 |
| ① 花が開く前の写真 | ② 鮮やかに咲く彼岸花 |
 |
 |
| ③ 土手に群生する彼岸花 | ④ 群がるように咲く |
9月下旬~10月初旬に撮影した写真です。(愛知県)
「彼岸=ひがん」とは仏教に由来する言葉で、迷いや苦しみのない清らかな極楽浄土を指します。”悟りの世界”や”あの世”と言った意味もあります。対義語は「此岸=しがん」で、煩悩や迷い、苦しみに満ちた衆生(しゅじょう)の世界(我々が住む現実の世界)です。
(1)異名・別名が多い
良く知られた別名には「曼珠沙華=まんじゅしゃか・まんじゅしゃげ」があります。仏典に由来した名前で、サンスクリット語で「天界に咲く花」「見る者の心を柔軟にする」といった意味があるそうです。
- 幽霊花:根や茎・花に強い毒性(毒花とも呼ばれます)があり、土葬の時代にモグラなどから遺体を守るために墓地に植えられていたことが由来とされています。他にも「死人花」「地獄花」「狐花(きつねばな)」「灯籠花(とうろうばな)」など、怖いイメージを連想させる名前も少なくありません。
- 天蓋花(てんがいばな):花の形が仏具の天蓋(下記の写真を参照)に似ていることが由来です。
- 葉見ず花見ず(はみずはなみず):花が咲く時期には葉がなく、葉がある時期には花がないという特徴からです。たしかに「シダの葉」などの草木、同じ季節に咲く「おしろい花」などの中に、突然のように現れる姿も見かけます。
- リコリス:(彼岸花の学名が「Lycoris」であることから)
- レッドスパイダーリリー:英語での名前で花びらが蜘蛛の足のように見えることからです。
 |
 |
| ⑤ 仏具の天蓋 | ⑥ 仏具の天蓋 |
⑤と⑥は天蓋花の由来となった仏具の「天蓋=てんがい」です。
(2)白い花の「白花曼珠沙華」
白色(淡い黄色、クリーム色かな?)の彼岸花。「白花曼珠沙華=シロバナマンジュシャゲ」と呼ばれ、赤い彼岸花と彼岸花の仲間である「ショウキズイセン=黄色の花」の自然交雑種だと考えられており、比較的珍しいようです。(10月初めころに撮影)
(3)夜に咲く彼岸花
夜に萎んでしまう花も多いですが、彼岸花は1日を通して咲くようです。

夜8時頃に撮影(9月末)
(4)開花時期には葉っぱがない!
彼岸花は開花時期(9月中旬~10月初旬)に、茎に葉っぱをつけません。葉っぱは花が枯れた(10月中旬~)から春にかけつけ5月頃に枯れます。このため夏から開花時期には葉っぱのない状態になるということです。
 |
 |
| 開花時期に葉がない | 下から見た彼岸花 |
同じような特徴をもつ草花には、7月~8月に薄いピンク色の花を咲かせる「夏水仙=ナツズイセン」黄色い花を秋に咲かせる「鍾馗水仙=ショウキズイセン」などがあります。
(5)美しさに宿る畏怖の念

土手の雑草を刈りとられた後の風景。彼岸花だけ残されています。彼岸花の美しさ、さまざまな名前に秘められた歴史、言い伝えから、刈り取るのに躊躇するなど理由がありそうです。
(6)花言葉
「情熱」「独立」「悲しい思い出」「あきらめ」「また会う日を楽しみに」「再会」などが広く使われています。誕生花としては9月13日、9月15日、9月20日、9月23日とする場合が多いです。「ラジオ深夜便」の選定では彼岸の中日である9月23日の花としています。
(7)彼岸花を題材にした句
彼岸花や曼殊沙華は秋の季語です。
俳句では
- 「つきぬけて 天上の紺 曼珠沙華」山口誓子
- 「曼珠沙華 あつけらかんと 道の端」夏目漱石
- 「なかなか死ねない 彼岸花咲く」種田山頭火
短歌では
- 「秋の野に あまりに真赤な 曼珠沙華 その曼珠沙華 取りて捨ちよやれ」
北原白秋- 「彼岸花 咲ける間の道を行く 行き極まれば母に会ふらし」上皇后美智子 様
(8)彼岸花の属性など
園芸サイト等から引用しています。
- 原産国:中国(有史以前に渡来)
- 分布:北海道から沖縄・南西諸島まで広い範囲に自生。
- 開花時期:9月中旬から10月初旬
- 花弁の数:6つ
- 有毒植物:根や茎。花に毒性あり。
関連ページ